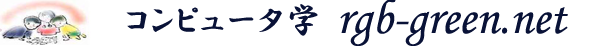数学の授業について
「数学」の授業をどう考え、長期展望に立ち、これからどう取り組んでいくかという問題について書く。
原点に返り、数学教育というものを考える。
現場の教師として、30年数学の授業をしている。その間、考えてきたことは頭の中にある。それを顕在化し、まとめてみたい。
3つの観点がある。
一つ目は、現在取り組んでいる「理」の研究の観点から。
二つ目は、学生の頃(20代)取り組んだ「『生き方の探求』としての数学教育」(修士論文)を30年ぶりに振り返る。
そして三つ目は、現場における数学の授業そのものから。
こうしたものをもとに53歳となった今、「数学の授業の体系」を作り上げていきたいと考えている。
何のために「数学」を学ぶのか、これは修士論文で取り組んできたテーマでもある。学生の頃出した結論は、『生き方を探求』するうえで数学的な考え方や見方、論理的に考えられる力、そうしたものは大切で授業を通じてそうした力を身につけさせる、それが数学を学ぶ意義で、そうした力を授業の中でどう養うか、授業構築法を考えていた。この時代は問題解決能力ということが言われた時代であり、その後の「生きる力」とも関係することである。
これをまとめたものが授業モデルである。(こちらを参照)
「理」の研究をライフワークとしてやるようになり、あらためて「何のために数学を学ぶのか」ということを考えたくなった。原点に戻ったわけである。
何のために数学を学ぶのか。それを問う前に、生徒たちは何のための学校へ来て学ぶのかを問いたい。それは、月並みな言い方だが、それは「生きる力」をつけるためと思う。「生きる力」とは、「陽気ぐらし」ができるための基礎力(学力、人間力)である。そして、次に「何のために数学を学ぶのか」を問う。それは、「陽気ぐらし」ができるための「数学的な力」をつけるためと考えたい。
「数学的な力」とは何か これを次に明らかにしたい。